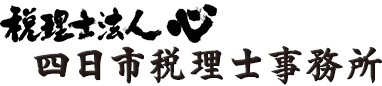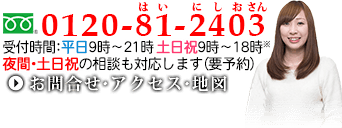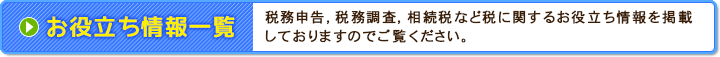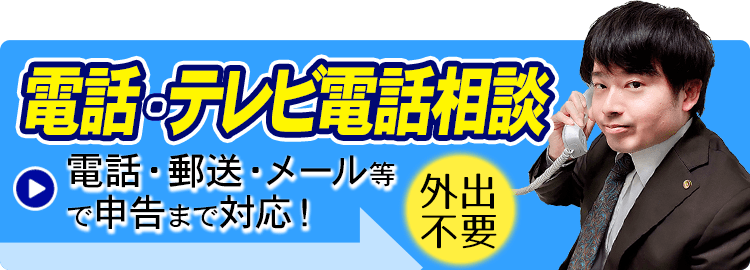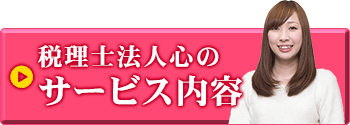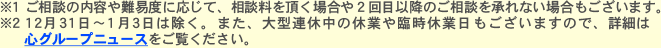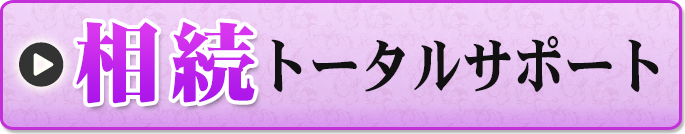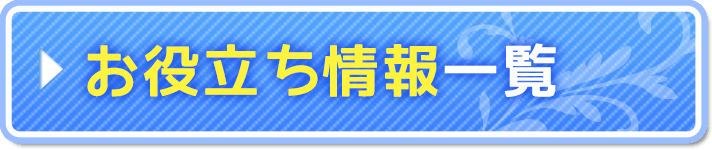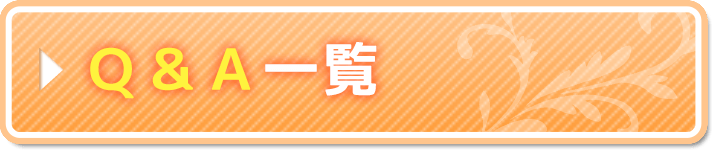不動産を法人化すると節税対策になりますか?
1 不動産の法人化は節税対策になり得る
賃料が発生する不動産を所有している場合は、不動産の賃料収入について、所得税、住民税を納付する必要があります。
個人に課税される所得税は、不動産の賃料収入については、総合課税で課税がなされることとなっており、給与所得等と合算した金額が大きくなればなる程、税率が増大する制度になっています。
最大では、所得税と住民税の合計で、約55%の課税がなされます。
このように、総合課税の所得税、住民税の負担が大きくなった場合には、法人化が有効な節税対策になります。
ここでは、法人化がどのような理由で節税対策になるかについて、説明したいと思います。
2 法人税の方が税率が低くなる可能性がある
現在では、法人税の実効税率(法人の事業税、住民税等を含んだ税率)は、約30%になっています。
先程の個人に課税される所得税、住民税の負担の最大値と比較すると、低めの税率になっています。
概ね、給与収入と賃料収入の合計額が1000万円を超えてくると、社会保険料等の負担を考慮しても、個人の所得税、住民税の方が、法人税よりも、税負担が重くなってきます。
このため、給与収入と賃料収入の合計額が1000万円を超えてくる場合は、法人化した方が、税負担を軽減できる可能性があることとなってきます。
3 最終的に収入を受け取る個人を分散することができる
法人化した場合は、賃料収入は法人が受け取ることとなります。
法人が受け取った賃料を、最終的に個人が受け取るようにするためには、個人を法人の役員にし、法人から個人に対して役員報酬を支払うことが考えられます。
このとき、複数の家族を役員にし、役員報酬を受け取る個人を複数にすると、一人一人が受け取る役員報酬を分散することができます。
このようにすると、一人一人の役員の所得の増加を抑えることができ、一人一人の役員に課税される所得税の税率を抑えることができます。
たとえば、2000万円の所得がある場合、所得税と住民税の税率は合計で50%になりますが、これを4人に分散すると、1人当たりの所得は250万円になり、所得税と住民税の税率を合計20%に抑えることができます。
このように、不動産の賃料収入を直接個人が取得するのではなく、間に法人をはさみ、複数の個人に分散して役員報酬を支払うこととすれば、所得税、住民税の負担をかなり、抑えることも可能になります。
ただ、この場合には、不動産の賃料収入を法人が取得する段階で法人税が発生し、これとは別に、個人が役員報酬を受け取る段階で所得税、住民税が発生していることに注意する必要があります。
税負担がどれだけ軽減されたかは、法人税の負担と所得税、住民税の負担の両方を考慮して、判断する必要があります。
4 個人に退職金を支払うことができる
法人化しておけば、退職した役員や従業員に対し、退職金を支払うことができます。
退職金についても、退職所得として所得税の課税対象になりますが、退職所得控除という、給与所得や不動産所得と比較し、かなり大きい非課税枠が設けられています。
たとえば、勤続年数が20年でしたら、退職所得控除の額は800万円となり、かなりの大きな非課税枠になります。
もちろん、退職所得控除を超える金額については課税対象になります。
この超える金額に適用される税率について、所得金額に2分の1を乗じて税率を乗じる計算を用いることとなるため、給与所得や不動産所得と比較し、半分程度に抑えられています。
このように、法人から個人に対して退職金を支払うこととしておけば、所得税、住民税の負担を抑えつつ、個人に収入を帰属させることができることとなります。
5 経費として認められる範囲が広い
法人については、個人と比較し、交際費や旅費等の経費が広く認められる傾向にあります。
経費が広く認められれば、その分、税負担を軽減することもできます。
これらの費用を経費として扱いやすいことも、法人化のメリットであると言えます。
ただし、法人であっても、事業とまったく関係のない支出まで、経費として認められるわけではありません。
法人化したものの、経費として扱ってもらえるって範囲が想定外に狭かったという話になることは、しばしばあります。
経費計上の範囲が広がることは結果論に過ぎず、経費として扱える支出を増やすことを主目的として法人化することは避けた方が良いのではないかと思います。
6 法人化のデメリット
他方で、法人化については、デメリットもあります。
先に述べた、法人税と所得税、住民税の両方の負担が発生すること以外に、以下のデメリットがあります。
① 設立時のコスト、毎年の会計、税務処理のコストが発生する。
② 社会保険に加入する必要がある。
法人化を検討する際は、こうしたデメリットも踏まえつつ、どれだけのメリットが得られるかを考慮して、実際に法人化するかどうかを決定する必要があると言えます。