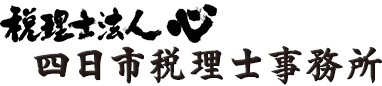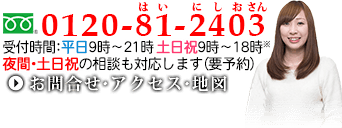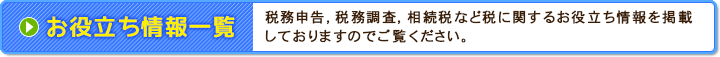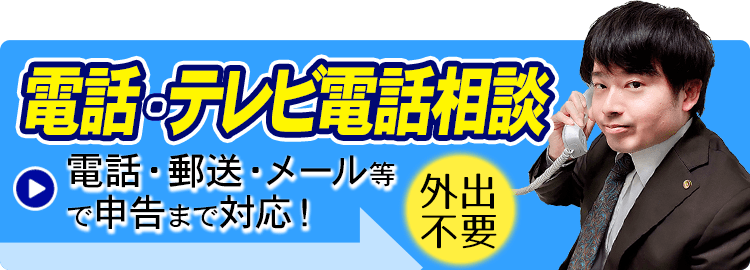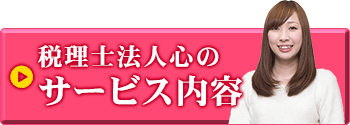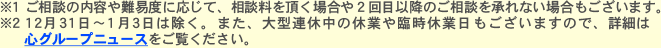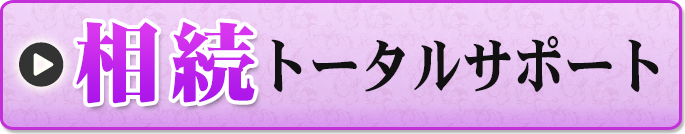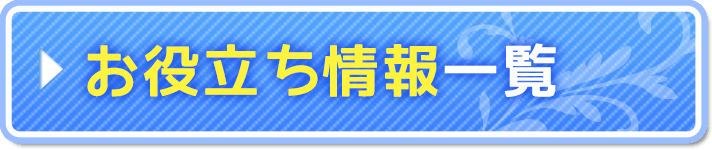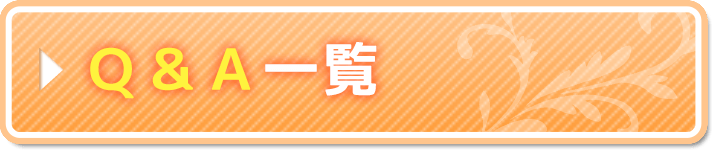医療費控除をする場合、確定申告はどのように行うのですか?
1 医療費控除について
1年間(1月1日から12月31日)までに支払った医療費が一定額を超える場合、翌年の3月15日までに確定申告を行い、医療費控除の適用を受けることにより、所得税を減額することができます。
給与所得や年金所得がメインであり、所得税の源泉徴収がなされている場合は、医療費控除の適用を受けることにより、源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。
また、事業所得がメインであるときも、納付すべき所得税を減額できる可能性があります。
ここでは、医療費控除を利用して確定申告をする場合の流れについて、説明したいと思います。
2 医療費についての資料の準備
⑴ 医療費控除の対象になると医療費
まず、1年間に支払った医療費の資料を準備する必要があります。
医療費としては、病院代や薬代が代表的なものになります。
治療目的のための費用であれば、保険外診療であっても、医療費控除の対象になります。
いわゆる美容整形のための費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象になるのは、病院代や医薬品代だけではありません。
まず、介護施設の費用が医療費控除の対象になることがあります。具体的には、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院については、利用料の全額が医療費控除の対象になります。特別養護老人ホームについては、利用料の半額が医療費控除の対象になります。
また、病院までの交通費についても、医療費控除の対象になります。ただ、タクシー代については、歩行が困難である等の事情がある場合に限り、控除対象になります。
他にも、おむつ代については、自治体において、いわゆるおむつ使用証明書の発行を受けることができれば、医療費控除の対象にできます。
医療費控除の対象になるのは、1年間に支払った医療費になります。
治療を受けたり、請求書をもらったりしたのは今年だけれども、まだ支払が完了していない医療費については、その年分の確定申告では医療費控除の対象にすることはできません。
医療費控除の対象になるのは、ご自身の医療費だけではありません。
生計を一にする親族の医療費であり、ご自身が負担したものについても、医療費控除の対象になります。
同居している親族であれば、おおむね生計を一にする親族になります。
また、別居していても、生活費の送金がなされていたり、余暇のときには一緒に生活をしていたりする親族については、生計を一にする親族になります。
⑵ 資料の集め方
それでは、1年間に支払った医療費についての資料は、具体的にどのように準備すれば良いのでしょうか?
1年間に支払った医療費の領収書が残っている場合は、それぞれの領収書の金額を合計することにより、医療費を算定することが考えられます。
介護施設の利用料、交通費等についても、領収書を残しておく必要があります。
領収書が残っていない場合は、病院に問い合わせを行い、医療費の証明書を発行してもらう必要があります。
とはいえ、すべての領収書を残しておき、これを合算して医療費を計算するのは大変です。
国民健康保険や健康保健組合の場合は、医療費のお知らせ等の名称で、毎年秋頃に、医療費の総額が記載された書類を送付してきます。
このように、医療費のお知らせがある場合は、個別に領収書を残しておかなくても、医療費のお知らせに記載された金額を用いることで、医療費控除を利用することができます。
なお、医療費のお知らせに記載された金額と領収書に記載された金額が異なっていることがありますが、どちらの金額で申告しても構いません。
医療費のお知らせには、1月から9月までの医療費は記載されていますが、10月から12月の医療費は記載されていません。このため、医療費のお知らせに記載がない期間の医療費については、別途、領収書を残しておく必要があります。
また、保険診療でない治療については、医療費のお知らせには治療費が記載されません。保険診療でない場合は、別途、領収書を残しておく必要があります。
介護施設の費用、交通費等についても、医療費のお知らせには記載されませんので、領収書を残しておく必要があります。
3 補てんされる金額についての資料の準備
それぞれの医療費からは、補てんされる金額を差し引くこととなっています。
医療費に対する補てんとは、保険会社から支払われた医療保険金、自治体から支給された高額療養費等になります。
医療保険金、高額療養費等で補てんがあったときは、その分、医療費の負担が生じないこととなりますので、医療費控除の対象外とされるのです。
このため、これらの金額が確認できる書類についても、準備しておく必要があります。
ここでいう補填される金額は、1月1日から12月31日までに支払った医療費に対応する補てんのことを言います。
たとえば、令和6年12月に医療費を支払い、令和7年2月に高額療養費が支給されたときは、この高額療養費は、令和6年に支払った医療費に対応するものとなりますので、令和6年の医療費から差し引かれることとなります。
高額療養費の支給が確定申告の期限よりもあとになるときは、支給の予定金額によって申告したり、修正申告したりする必要が生じることもあります。
4 医療費控除の明細書の作成
資料が準備できたら、医療費控除の明細書のフォーマットを取得し、作成することとなります。
医療費控除の明細書のフォーマットは、国税庁のホームページで入手することもできますし、税務署の窓口で入手することもできます。
医療費控除の明細書には、資料に基づき、人別、支払先別の医療費の合計額を記載することとなります。
イメージとしては、自分のA病院の医療費は合計●円、自分のB病院の医療費は合計●円、配偶者のC病院の医療費は合計●円、配偶者のD病院の医療費は合計●円のような形でまとめることとなります。
また、それぞれの医療費について、補填される金額も記載します。
これらの金額をすべて合計し、医療費の合計額、補てんされる金額を確定することとなります。
5 確定申告書の作成、提出
あとは、確定申告書を作成し、提出することとなります。
以下の金額が医療費控除の額となりますので、確定申告書の第1表に計算結果を記載します。
⑴ 1年間の所得金額が200万円以上の場合
医療費の合計額-補填される金額-10万円
⑵ 1年間の所得金額が200万円未満の場合
医療費の合計額-補填される金額-総所得額の5%
※ 医療控除の額は200万円が上限になります。
確定申告書には、医療費控除の明細書を添付して提出します。
もとになった領収書等の資料については、確定申告書に添付する必要はありません。
ただし、領収書等については、5年間は保管しておく義務があります。
確定申告書が完成したら、申告の期間内に、管轄税務署に確定申告書を提出します。
申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日になります。
ただし、源泉徴収された所得税の還付を受ける場合は、翌年の3月15日が経過したとしても、その後5年間は、申告書を提出し、所得税の還付を受けることができます。
青色申告に関するQ&A 個人事業主から法人化するタイミングについてのQ&A