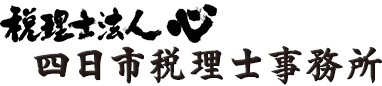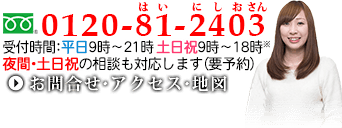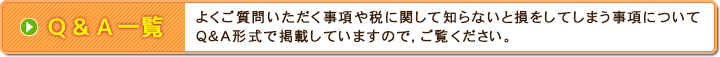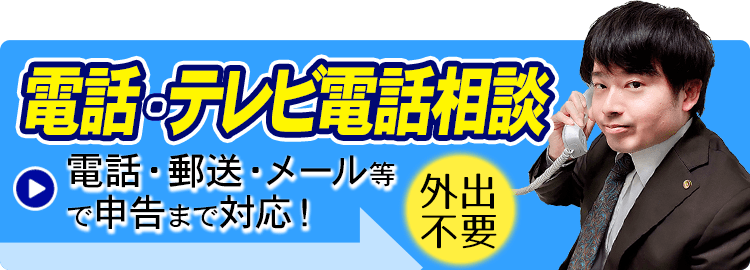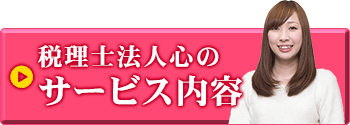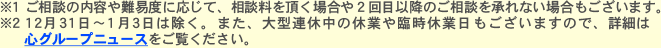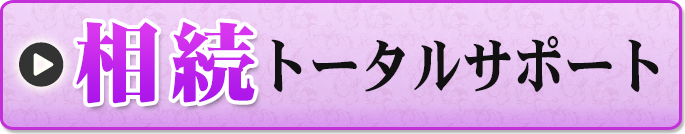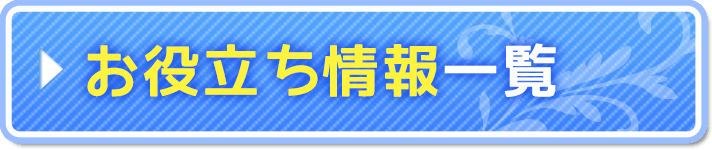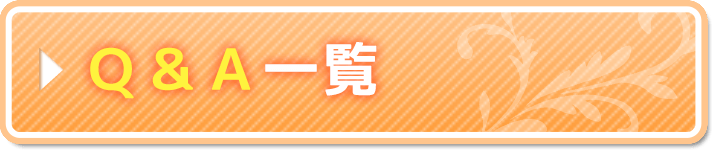所得税の計算方法
1 所得税の計算をしなければならないケース
給与収入や年金収入で生活している場合は、所得税が課税されるとしても、源泉徴収がされているため、別途、申告や納付をしなくてもよい場合が多いです。
扶養控除や生命保険料控除等の控除の制度を利用できる場合も、年末調整時に勤務先に資料を提出すれば、年末調整後に払い過ぎた分の精算を受けることができますし、そもそも、こうした制度を利用しないままでいるということもあります。
このため、長い間、所得税をほとんど意識することなく、生活を続けているという方も多いのではないかと思います。
もっとも、このような方であっても、以下のような場合には、所得税の確定申告を行い、所得税の計算を行わなければならなくなることがあります。
⑴ 副業を行っている場合
副業を行ったり、副収入が発生したりしている場合です。
⑵ 臨時の収入が発生した場合
不動産を売却したり、保険を解約したりする等、臨時の収入が発生した場合です。
2 所得税の計算方法
⑴ すべての所得を把握する
まず行うべきなのは、すべての所得の把握です。
本業・副業の給与所得や年金について、源泉徴収票が発行されている場合は、源泉徴収票の収入・所得の記載を転記することとなります。
源泉徴収票がない所得については、実際に1年間に入金等があった金額を合算し、経費を控除する等して、所得を算定する必要があります。
ア 臨時の収入があった場合
保険の解約などにより、臨時の収入があった場合は、こちらも所得に加算する必要があります。
どの所得に該当するかは、その収入によって異なる部分です。
保険の解約の場合は、返戻金額から払込済保険料を差し引いた金額が一時所得となります。
イ 不動産を売却した場合
不動産を売却した場合は、分離課税がなされます。
参考リンク:国税庁・申告分離課税制度
具体的には、不動産の売却金額から、取得費や譲渡費用を差し引いた金額について、15.315%(復興特別加算税を含む)の課税がなされます。
このため、別途、譲渡所得の明細も作成する必要があります。
⑵ 各種控除の適用の検討をする
次に行うべきなのは、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除(配偶者特別控除)、扶養控除、住宅ローン控除等の適用の検討です。
これらの控除を利用することができる場合は、所得税が軽減されますので、利用の可否を検討するのがよいかと思います。
⑶ 税額を計算する
そして、所得の把握や適用可能な控除の検討を行った後に行うべきなのは、税額の計算です。
所得や控除等について確定申告書の書式に記入していき、最終的な税額を算定することとなります。
確定申告の申告から納付までの流れ 副業でかかる税金と確定申告の方法